インプラントは、失った歯を補い、自然な噛み心地を取り戻せる先進的な治療法です。
しかし、治療後のケアを怠ると「インプラント周囲炎」というトラブルが起こる可能性があることをご存知でしょうか?
「インプラント治療後も問題なく過ごせるのだろうか?」
「インプラント周囲炎って何?どうやって防げばいいの?」
「長持ちさせるために、どんなケアが必要なの?」
こうした疑問や不安を抱えている方に向けて、この記事では、歯科医師が
- インプラント周囲炎の症状と進行度
- 症状が起こる原因
- 予防方法
までをわかりやすく解説します。
治療後のインプラントを長く健康に保つためには、事前に正しい知識を持つことが重要です。
ぜひ最後までお読みいただき、インプラント治療をより安心して受けていただければと思います。
下記の動画では、インプラントとはどんなものか、他の治療法と比べたメリット・デメリットについて詳しく解説しています。
インプラントを検討している方が、まず押さえておくべき知識をまとめていますので、ぜひ併せてご覧ください。
YouTube動画:インプラントのメリット・デメリット【人気歯科医が徹底解説】
当医院では、患者様一人ひとりの状況やお悩みに合わせた精密な診断と適切な治療計画をご提案しています。
無料相談を電話とメールで承っていますので、治療への不安や疑問を、ぜひお気軽にご相談ください。
インプラント治療を検討する際には、信頼できる歯科医院を選ぶことが何より大切です。
医院の設備や医師の経験、治療の実績をしっかり確認し、自分に合った医院を選びましょう。
インプラント治療を成功させるための詳しいポイントは、下記の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。
福岡県大野城市やその周辺にお住まいで通える方は、ぜひ「はち歯科医院」にご相談ください。
一方で、当医院に通えない地域の方は、下記の記事を参考にインプラント治療を行う医院を慎重に選んでくださいね。
下記の記事では、「インプラント治療にかかる費用の相場や内訳」や「インプラント治療費用の支払いで負担を抑えるポイント」について、詳しく解説しています。
こちらもぜひ併せて読んでみてくださいね。
目次
Ⅰ インプラント周囲炎とは|原因は?歯周病とは何が違う?
インプラント周囲炎は、インプラントを支える歯ぐきや骨に炎症が生じる状態です。
治療を怠ると最終的にはインプラントが脱落することもあります。

健康な状態を保つためには、治療後のケアが欠かせません。
また、インプラント周囲炎は、天然歯に発生する歯周病と似た特徴を持っています。
インプラント周囲炎と歯周病は、どちらも細菌感染が原因となり、歯ぐきや骨に炎症を引き起こす病気です。
人工歯根か天然歯かという違いはありますが、症状や予防・治療の基本はほとんど同じです。
どちらも適切な清掃や定期的な歯科メンテナンスが重要で、進行した場合には専門的なクリーニングや外科手術が必要になることがあります。
Ⅱ インプラント周囲炎の症状と進行度
インプラント周囲炎は、進行度に応じて下記のような段階に分けられます。
- 初期段階(インプラント周囲粘膜炎)
- 中期段階(軽度~中等度のインプラント周囲炎)
- 進行段階(重度のインプラント周囲炎)
- 最終段階(インプラント脱落)
それぞれの症状や状態を理解することで、適切な対応が可能になります。

各段階について解説します。
初期段階(インプラント周囲粘膜炎)
インプラント周囲炎の初期段階では、自覚症状がほとんどないため、見逃されやすい状態です。
しかし、次のような兆候が現れる場合があります。
- 歯ぐきが赤く腫れる
- ブラッシング時に出血する
- インプラント周囲に違和感や軽い痛みを感じる
- 口臭が強くなる
炎症が歯ぐきの表面にとどまり、骨にはまだ影響がありません。

この段階でケアを強化すれば、症状を改善できます。
これらの症状が現れた場合は、早めに歯科医院で診察を受けることが重要です。
周囲炎を放置すると、次の段階に進行し、インプラントを支える骨が溶け始める恐れがあります。
中期段階(軽度~中等度のインプラント周囲炎)
- 歯ぐきの腫れが悪化する
- 出血が日常的に起こる
- 痛みや違和感が強まる
- 口臭がさらに悪化する
炎症が骨に広がり、インプラントを支える骨が一部溶け始めます。

この段階になると専門的な治療が必要になります。
進行段階(重度のインプラント周囲炎)
- 歯ぐきが退縮し、インプラントが露出する
- インプラントが動揺する(ぐらつきが生じる)
- 強い痛みと慢性的な出血が続く
骨吸収が進行し、インプラントの安定性が著しく低下します。

さらに放置するとインプラントの脱落のリスクが高くなります。
最終段階(インプラント脱落)
- 骨の大部分が失われ、インプラントを支えられず、グラグラと動く
- インプラントが自然に抜け落ちる

再治療には骨移植や再インプラント治療が必要になることが多く、治療が難しくなります。
進行したインプラント周囲炎では、以下の治療法が必要になる場合があります。
- 炎症を抑える外科手術
感染部分を除去し、炎症を抑えます。 - 骨再生治療
骨移植や再生材料を使用し、失われた骨を再生します。
また、インプラント周囲炎を放置すると、骨が溶けるだけでなく、顎全体に炎症が広がる可能性があります。

最悪の場合、再治療ができないケースもあるため、早期発見と対応が何よりも重要です。
Ⅲ インプラント周囲炎を引き起こす原因と6つの要因
インプラント周囲炎は、主に細菌感染という直接的な「原因」によって発生します。
その背景にはさまざまな「要因」が絡み合っている場合が多いです。
これらの要因を理解し、適切に対処することで、周囲炎の発生リスクを大幅に低減できます。

インプラント周囲炎を引き起こす主な6つの要因を、それぞれ詳しく解説します。
- プラークコントロールの不備
- メンテナンス不足
- 喫煙習慣や糖尿病などの疾患
- 不規則な食生活や口腔ケアの不足
- 噛み合わせの不具合(咬合力の過負荷)
- 免疫力の低下
原因⑴:プラークコントロールの不備
歯垢(プラーク)が適切に除去されないと、細菌が繁殖し、炎症を引き起こします。
インプラントは天然歯とは異なる形状を持つため清掃が難しく、場合によっては、専用の歯ブラシやデンタルフロスの使用が求められます。
不十分なプラークコントロールは、インプラント周囲炎の最も一般的な原因の一つです。
原因⑵:メンテナンス不足
治療後の定期メンテナンスを怠ると、歯垢や歯石がたまりやすくなり、炎症の原因となります。
原因⑶:喫煙習慣や糖尿病などの疾患
喫煙や糖尿病などが、インプラント周囲炎を引き起こすリスクを高めます。
これらの習慣や疾患を適切に管理することが予防の第一歩です。
原因⑷:不規則な食生活や口腔ケアの不足
不規則な食生活や口腔ケアの不足は、細菌の増殖を助長します。
習慣を見直し、リスクを減らす行動を心がけましょう。
原因⑸:噛み合わせの不具合(咬合力の過負荷)
インプラントに過剰な咬合力(噛み合わせの力)がかかると、周囲の組織にストレスが加わり、炎症を引き起こすリスクが高まります。
特に、歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合、インプラント周囲の骨や歯ぐきに負担がかかりやすくなります。
原因⑹:免疫力の低下
免疫力が低下すると、体が細菌と戦う力が弱まり、インプラント周囲炎を引き起こしやすくなります。
免疫力の低下は、栄養不足、ストレス、睡眠不足、慢性的な疾患(例:リウマチや慢性炎症性疾患)などが原因となります。
健康的な生活習慣を維持し、免疫力を高めることが予防に役立ちます。
Ⅳ インプラント周囲炎の予防対策
インプラント周囲炎を予防するには、毎日の清掃と歯科医院での定期メンテナンスが不可欠です。

主な6つの予防対策を、それぞれ詳しく解説します。
- 洗口液の使用
- 正しいブラッシング方法や清掃補助器具の使用
- 禁煙やバランスの取れた食事を心がける
- インプラントに負担をかける習慣を避ける
- 歯科医院での定期的なメンテナンス
- セルフチェックの習慣化
⑴ 正しいブラッシング方法や清掃補助器具の使用
正しいブラッシング方法やデンタルフロスの使い方を習得することが特に重要です。
インプラントの清掃には、通常の歯ブラシだけでなく、専用のインプラント用歯ブラシや歯間ブラシ、デンタルフロスが効果的です。
⑵ 洗口液の使用
洗口液の使用も予防に効果的です。
抗菌作用のある洗口液を活用することで、インプラント周囲の細菌を抑制し、炎症を防ぐことができます。
⑶ 禁煙やバランスの取れた食事を心がける
禁煙やバランスの取れた食事を心がけることで、インプラント周囲炎のリスクを軽減できます。
また、睡眠を十分に取り、ストレスを溜めないようにすることも、炎症予防に効果的です。
⑷ インプラントに負担をかける習慣を避ける
治療後に噛み合わせの変化が起こると、インプラントに過剰な負担がかかり、周囲炎のリスクが高まります。
必要に応じて歯科医院で調整してもらうことが重要です。
特に歯ぎしりや食いしばりがある方には、ナイトガード(マウスピース)の使用が推奨されます。
⑸ 歯科医院での定期的なメンテナンス
歯科医院での定期的なメンテナンスでは、インプラントの状態や歯ぐきの健康状態を確認し、必要に応じて専門的なクリーニングや治療を行います。
治療後は、定期的に歯科医院を訪れ、インプラントの状態をチェックしてもらうことが重要です。
これにより、周囲炎の発生を未然に防ぐことができます。
下記の記事では、「歯科医院でのメンテナンスが重要な理由」や「セルフケアと歯科医院でのメンテナンスの役割の違い」について、詳しく解説しています。
⑹ セルフチェックの習慣化
インプラント周囲炎を早期に発見するために、次のポイントをセルフチェックする習慣をつけましょう。
- 歯ぐきが赤く腫れていないか
- ブラッシング時に出血していないか
- インプラント周囲に違和感がないか
- 口臭が気にならないか
これらの兆候に気づいたら、すぐに歯科医院を受診することが大切です。
Ⅴ はち歯科医院から、インプラント治療を検討している方へのメッセージ
インプラント治療は、失った歯を補い、自然な噛み心地と美しい口元を取り戻せる選択肢です。
しかし、その効果を長く維持するためには、治療後の適切なケアが欠かせません。
特にインプラント周囲炎の予防と早期発見には、日々のセルフケアと歯科医院での定期メンテナンスが重要です。

馬場院長
当医院では、患者様一人ひとりの状況やご要望に合わせた、最適な治療プランをご提案しております。
治療前の丁寧なカウンセリングから、手術、そして治療後のメンテナンスまで、全てのステップにおいて、患者様のニーズに寄り添いながら、最適なサポートを行います。
私たちは、患者様一人ひとりの健康と笑顔を守るために、常に最高の治療を目指して提供しています。
もしインプラント治療に関して不安や質問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
インプラント治療を検討する際には、信頼できる歯科医院を選ぶことが何より大切です。
医院の設備や医師の経験、治療の実績をしっかり確認し、自分に合った医院を選びましょう。
インプラント治療を成功させるための詳しいポイントは、下記の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。
福岡県大野城市やその周辺にお住まいで通える方は、ぜひ「はち歯科医院」にご相談ください。
一方で、当医院に通えない地域の方は、下記の記事を参考にインプラント治療を行う医院を慎重に選んでくださいね。
下記の記事では、「インプラント治療にかかる費用の相場や内訳」や「インプラント治療費用の支払いで負担を抑えるポイント」について、詳しく解説しています。
こちらもぜひ併せて読んでみてくださいね。
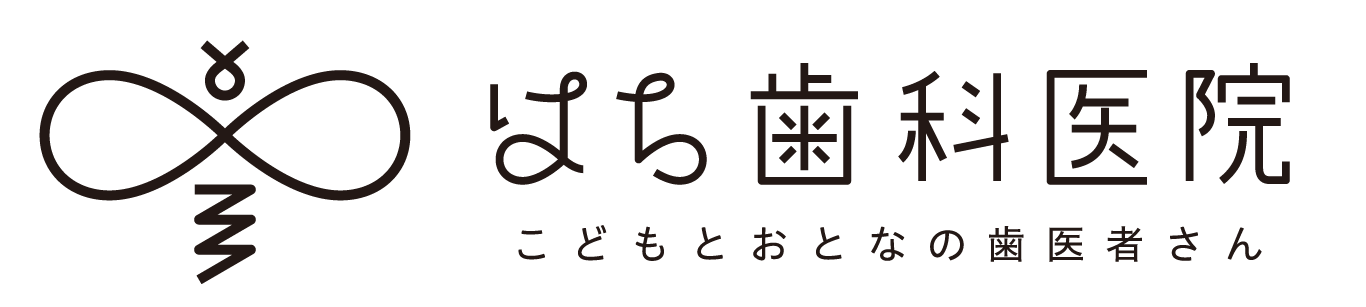
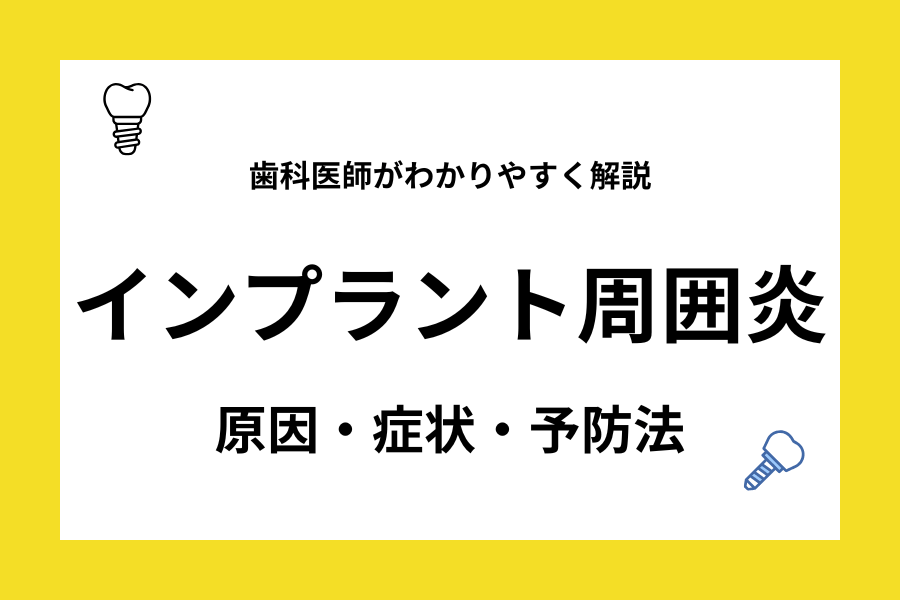
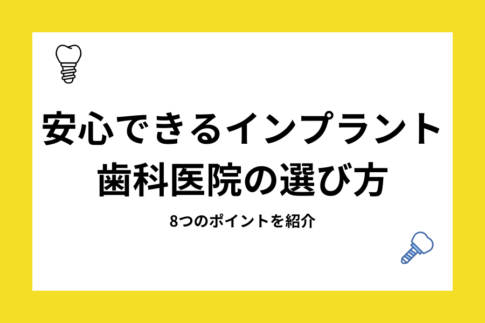
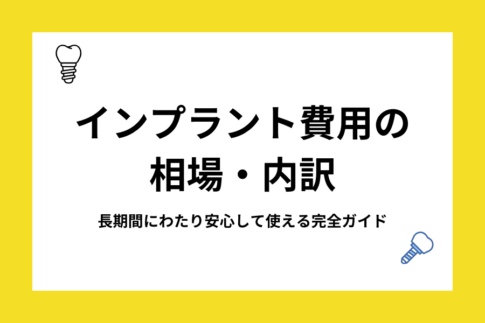
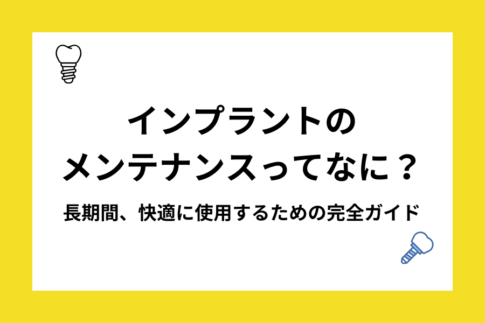
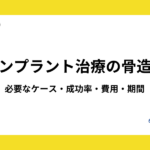
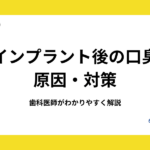

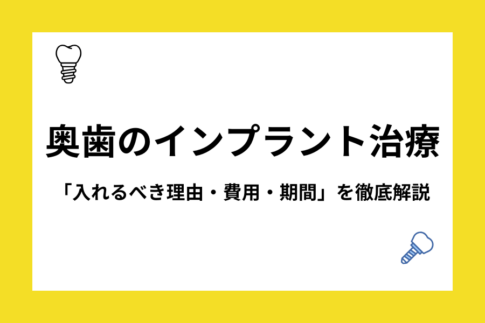

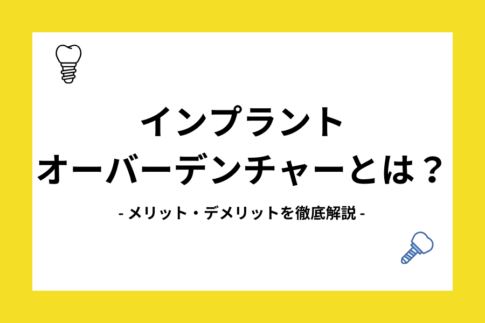
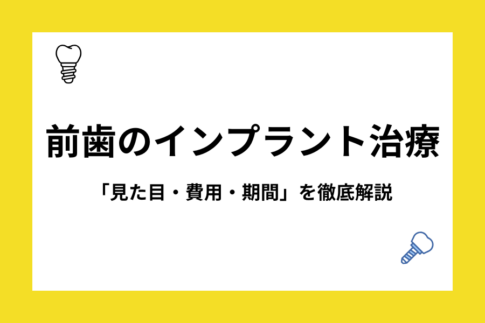
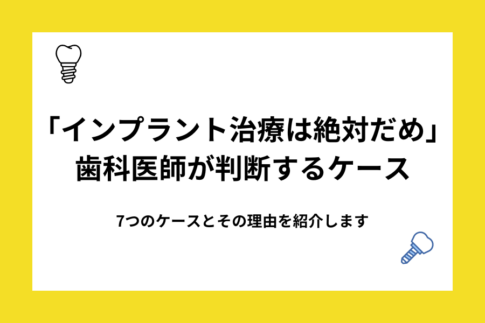


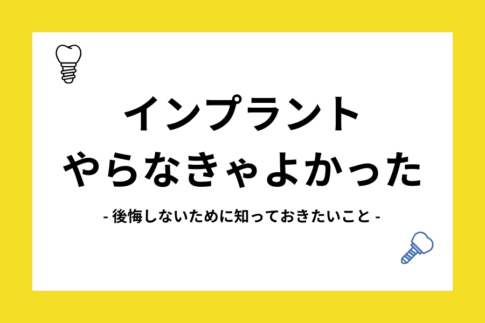
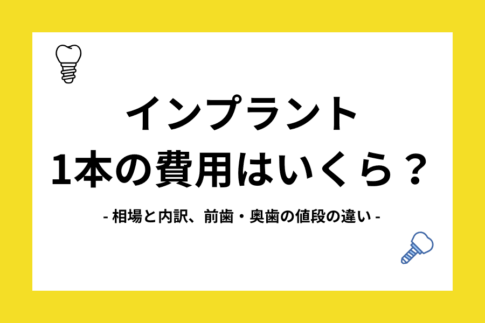
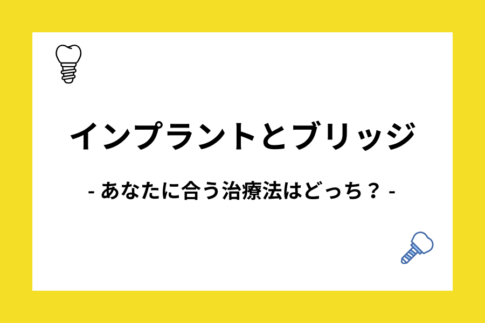
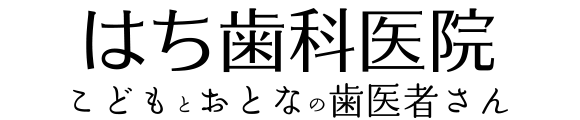
馬場院長
この記事を通して、インプラントのケア方法や日常生活での注意点を一緒に学びましょう。